厄年・厄除け厄祓いドットコム
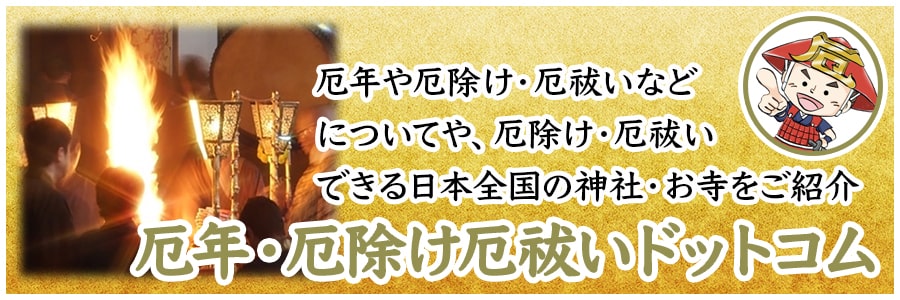
【厄年・厄除け厄払いの専門サイト】厄年や厄除け・厄払いなどについてや、厄除け・厄払いできる日本全国の神社・お寺をご紹介
更新
本厄・大厄とは?本厄・大厄―女性・男性 一覧早見表

『本厄・大厄』の女性・男性の早見表を用意しました。
今年2023年の本厄・大厄を女性・男性ともに調べられます。
またその前後の2020年〜2025年まで、本厄の年と生まれ年が調べられるように一覧表の形で掲載しております。
女性の本厄 年齢は19歳、33歳、37歳、61歳、うち大厄は33歳
男性の本厄 年齢は25歳、42歳、61歳、うち大厄は42歳
こちらのページもおすすめ

江戸やくよけ祖師妙法寺の本厄御守|撮影:厄年・厄除け厄祓いドットコム
本厄・大厄―女性 一覧早見表
注:(*)の本厄の年齢は数え年での年齢です
| 西暦 年号 |
本厄 19歳* | 本厄 33歳* (大厄) |
本厄 37歳* | 本厄 61歳* |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 令和7年 |
2007年 平成19年生 いのしし |
1993年 平成5年生 とり |
1989年 昭和64年生 平成元年 へび |
1965年 昭和40年生 へび |
| 2024年 令和6年 |
2006年 平成18年生 いぬ |
1992年 平成4年生 さる |
1988年 昭和63年生 たつ |
1964年 昭和39年生 たつ |
| 2023年 令和5年 |
2005年 平成17年生 とり |
1991年 平成3年生 ひつじ |
1987年 昭和62年生 うさぎ |
1963年 昭和38年生 うさぎ |
| 2022年 令和4年 |
2004年 平成16年生 さる |
1990年 平成2年生 うま |
1986年 昭和61年生 とら |
1962年 昭和37年生 とら |
| 2021年 令和3年 |
2003年 平成15年生 ひつじ |
1989年 昭和64年 平成元年生 へび |
1985年 昭和60年生 うし |
1961年 昭和36年生 うし |
| 2020年 令和2年 |
2002年 平成14年生 うま |
1988年 昭和63年生 たつ |
1984年 昭和59年生 ねずみ |
1960年 昭和35年生 ねずみ |
注:(*)の本厄・大厄の年齢は数え年での年齢です

【厄除け・厄祓い 豆知識】
女性の厄年について(女性の厄年 年齢など)
本厄・大厄―男性 一覧早見表
注:(*)の本厄の年齢は数え年での年齢です
| 西暦 年号 |
本厄 25歳* | 本厄 42歳* (大厄) |
本厄 61歳* |
|---|---|---|---|
| 2025年 令和7年 |
2001年 平成13年生 へび |
1984年 昭和59年生 ねずみ |
1965年 昭和40年生 へび |
| 2024年 令和6年 |
2000年 平成12年生 たつ |
1983年 昭和58年生 いのしし |
1964年 昭和39年生 たつ |
| 2023年 令和5年 |
1999年 平成11年生 うさぎ |
1982年 昭和57年生 いぬ |
1963年 昭和38年生 うさぎ |
| 2022年 令和4年 |
1998年 平成10年生 とら |
1981年 昭和56年生 とり |
1962年 昭和37年生 とら |
| 2021年 令和3年 |
1997年 平成9年生 うし |
1980年 昭和55年生 さる |
1961年 昭和36年生 うし |
| 2020年 令和2年 |
1996年 平成8年生 ねずみ |
1979年 昭和54年生 ひつじ |
1960年 昭和35年生 ねずみ |
注:(*)の本厄・大厄の年齢は数え年での年齢です

【厄除け・厄祓い 豆知識】
男性の厄年について(男性の厄年 年齢は?)
本厄・大厄とは?

本厄とは厄年そのものの年(年齢)であり、いろいろな諸説がありますが、一生のうちで災難に遭うおそれが多い年だと言われています。
本厄の前の年を「前厄」、本厄後の年を「後厄」と言います。
具体的には
男性 25歳、42歳、61歳
女性 19歳、33歳、37歳、61歳
(上記年齢は「数え年」での年齢)
が男女それぞれ本厄(=厄年)にあたる年齢となります。
本厄の中でも
男性42歳、女性33歳は大厄(たいやく)
と言われ、男性女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年と言われています。
またその年齢で、語呂合わせで42歳は「死に」、33歳は「散々」に通じるからなどとということもあるようです。
前厄・本厄・後厄に関するアンケート
厄年に関するアンケートを行っています。こちらは前厄・本厄・後厄に関するアンケートです。回答していただくとすぐに回答結果が表示されます。
役割や環境の変化としての本厄・大厄の時期

※春日大社(奈良県奈良市)の本厄絵馬の様子
また男性は25歳頃に仕事の中心を担う
42歳頃には、現役を退いて隠居
女性は19歳頃に出産
33歳頃には子育ても一段落
といったように、厄年は社会的な役割や生活環境が変わる頃にあたることから、役割を担う年=『役年』から厄年になったといわれる説もあります。
厄年の風習は平安時代の陰陽道に起源があると言われており、現代とは結婚・出産の年齢も社会的環境も異なる時代の風習ではありますが、それでもやはり人間という生き物の根源に関わることでもあり、無関係と思えない側面もあります。
科学的根拠はありませんが、実際、女性の場合、33歳の厄年に、女性ホルモンやストレスなどから婦人科系の病気になる人が多く、また離婚率も、厄年に当たる31〜33歳が高くなるそうです。
男性の場合は大厄42歳前後は、大腸ガンや喉頭ガンの発生率が高くなっているという統計もあります。
また厄年の災難は、ご自分だけでなく親御さんや、お子様、仕事など周りの方にふりかかることもあります。ご自身とご家族、周りの方の心の安心にもつながるため、本厄、大厄の年は神社・お寺で厄除け・厄祓いを行なってもらいましょう。
また家族揃って、厄祓いをしておくことで、気持ちに落ち着きが生まれ、健康にも気をつける意識をもつことで、災いを回避することができることでしょう。
前厄・後厄の女性・男性一覧早見表ページはこちら

【厄除け・厄祓い 豆知識】
前厄ー女性・男性 一覧早見表

【厄除け・厄祓い 豆知識】
後厄ー女性・男性 一覧早見表
厄年・厄除け情報をどこよりも詳しく発信中!

サイトマスコットキャラ:厄丸くん
厄年に関するアンケートにご協力ください
厄年に関するアンケートを行っています。回答していただくとすぐに回答結果が表示され、みなさんの厄年への関心度合いを見ることができます。










 厄除け・厄払い 豆知識!
厄除け・厄払い 豆知識!